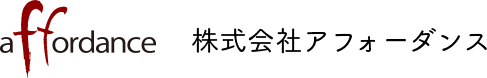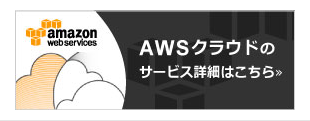デジタル導入の「教育先進国」で紙教育が復活? | 教育コラム

こちらは読売新聞の記事です。
「デジタル導入の「教育先進国」で成績低下や心身の不調が顕在化…フィンランド、紙の教科書復活「歓迎」」
この記事では、デジタル教育先進国が、教育へのデジタル技術の積極的な導入によって学力低下や心身の不調が顕在化し、見直しの動きが出ていると紹介しています。特に、かつて高い学力を誇ったフィンランドや、デジタル端末の配布を見送ったシンガポール、デジタル教科書の導入に慎重な意見が多い韓国の状況を詳しく伝えています。これらの国々では、子どもの集中力低下、デジタル依存への懸念、教師とのコミュニケーション不足などが問題視されています。
一方、日本は教科書を紙からデジタルに置き換える方向へ進んでおり、文部科学省主導の議論の危うさを指摘しています。海外の動向を十分に検討しないままデジタル化を推進することへの懸念が示されています。
日本がデジタル教育を推し進める動きに対し、海外の事例は重要な警鐘を鳴らしていると言えるでしょう。デジタル技術は、情報の収集、集約、展開(共有)という点においては非常に有効であり、教育現場においてもこれらの側面で積極的に活用すべきだと思います。例えば、最新の情報を瞬時に共有したり、多様なデータを集めて分析したり、生徒同士で意見交換をしたりする際には、デジタルの利便性は疑いようがありません。
しかし、教育の本質は知識の詰め込みだけではありません。思考力、集中力、創造性、そして人間関係を育むことも重要な要素です。これらの能力を育成する上では、必ずしもデジタルが最適とは限りません。記事にあるように、紙の教科書を読むことで得られる落ち着きや、鉛筆で書き込むことで深まる理解、直接的な対話によるコミュニケーションなどは、デジタルでは代替しにくいと考えられます。
特に、幼少期や発達段階においては、実物に触れたり、手を動かしたりする経験が不可欠です。デジタルデバイスの画面を見る時間が長くなることは、視力低下や運動不足、さらにはデジタル依存といった懸念も引き起こします。
したがって、日本のデジタル教育推進においては、「何でもデジタルに」という安易な方向へ進むのではなく、デジタルの強みと紙媒体の良さをしっかりと見極め、それぞれの特性を活かした教育を行うべきです。情報の効率的な活用にはデジタルを、深い思考や人間的な触れ合いには紙媒体や対面でのコミュニケーションを重視するなど、バランスの取れた教育こそが、子どもたちの健全な成長につながるのではないでしょうか。海外の失敗例を真摯に受け止め、拙速なデジタル化ではなく、慎重な議論と検証を行うことが求められます。
*本日のイメージ画像は、Canvaのマジック画像生成を用いて「フィンランドの小学生が勉強しているところ」というプロンプトで生成しました。
執筆者紹介

佐藤 大輔 satow@affordance.co.jp
株式会社アフォーダンス
エデュケーションサービス事業本部 エバンジェリスト
主に教育機関向けのGoogle Workspace等のクラウドサービスを活用した授業改善にかかるアドバイスや、情報セキュリティにかかる教育・改善支援を実施。エデュケーションサービス事業のエバンジェリスト(伝道師)として学校のGIGAスクール構想推進や運営支援サービスを行う。学校の先生向けの学校著作権研修、保護者、児童生徒向けの情報モラル・デジタルシディズンシップ研修なども実施。